なぜ私たちは、流行に流されてしまうのでしょうか?
新しいカフェ、話題のドラマ、SNSでバズってるあの曲…。
「チェックしなきゃ」「乗り遅れたくない!」って思っていませんか?
発信している人などは特に感じているかも。

別に興味なかったはずなのに、みんなが良いって言うからつい…

周りに合わせなきゃって、本当の気持ちを隠してしまう…
そんな経験、一度や二度じゃないかもしれませんね。
実は、流行に流されてしまうのは、人間の本能や心の仕組みが深く関わっているからなんです。決して、意志が弱いとか、自分がない、ということだけではありません。
でも、その仕組みを知って、少し意識を変えるだけで、情報の波に溺れず、もっと心地よく、自分らしくいられるようになるかもしれません。
この記事では、流行に流されてしまう「ちょっと耳の痛い理由」にも触れながら、どうすれば自分軸でいられるのか、そのヒントを探っていきます。

いやー、わかるなぁ…。僕もつい、周りが盛り上がってると気になっちゃうタイプ。でも、なんでなんだろう?ってずっと思ってたんだよね。
⏱️ この記事のポイント
①流されずに「自分」でいるための、今日からできる具体的なヒント。
②流行に流されるのは、脳の「安心したい」本能が関係している。
③「乗り遅れたくない!」気持ちの裏には、自信のなさや承認欲求が隠れている可能性も
④SNSや情報のシャワーが、無意識のうちに私たちを流している仕組み。
【おすすめ本】
📚 『反応しない練習 あらゆる悩みが消えていくブッダの超・合理的な「考え方」』 / 草薙龍瞬
👆周りの情報や感情に心がザワザワしてしまう時に読むと、スーッと楽になりますよ。「そういうことか!」と腑に落ちる考え方が、難しい言葉ゼロで解説されています。流行への過剰反応も、これで少し落ち着くかも。
📚 『事実はなぜ人の意見を変えられないのか』 / ターリ・シャーロット
👆なぜ私たちは、客観的な事実よりも「みんなが言っていること」や「信じたいこと」を優先してしまうのか?脳の仕組みから分かりやすく解説。流行に流されるメカニズムを知る上で、とても興味深い一冊です。

そういえば、最近移動時間にAudibleで本を「聴く」のがマイブームなんだけど、これがなかなか良くて。手がふさがってても、勝手に物語が進んでいくの、ラクだし集中できるんだよね。しかも知識がついて、語彙力上がって癒される。
無料体験もできるみたいなので、「へぇ〜」って思った方は、試しに聴いてみるのもアリかもですよ〜。たまーに2か月90円とかで試せるのもあるのでぜひ。👇
1. 「みんなと一緒」が心地いい?脳が求める安心感の罠

まず、知っておきたいのは、「仲間外れを恐れる」のは、ある意味、人間の本能だということです。
大昔、人間が集団で生きていた時代、グループから外れることは、生き残る上で非常に危険なことでした。だから私たちの脳には、「みんなと一緒だと安全だ」「周りに合わせよう」というプログラムが、深く刻み込まれているんです。
流行に乗ることで、「自分は集団の一員だ」「間違っていない」という安心感を得られます。すると、脳の中では「やったね!」とばかりに、快感物質であるドーパミンが放出される、なんて研究もあるようです。(参考:社会的報酬に関する脳科学研究など)
つまり、「流行りものが好き!」というよりは、「仲間外れになりたくない」「安心したい」という無意識の欲求が、私たちを流行へと駆り立てているのかもしれません。

へぇー!本能レベルの話だったんですね!だから、みんなが持ってるものとか、話題にしてることとか、つい気になっちゃうのかも。
2. 「乗り遅れたくない!」心の声の正体は?【ちょっと耳が痛い話】

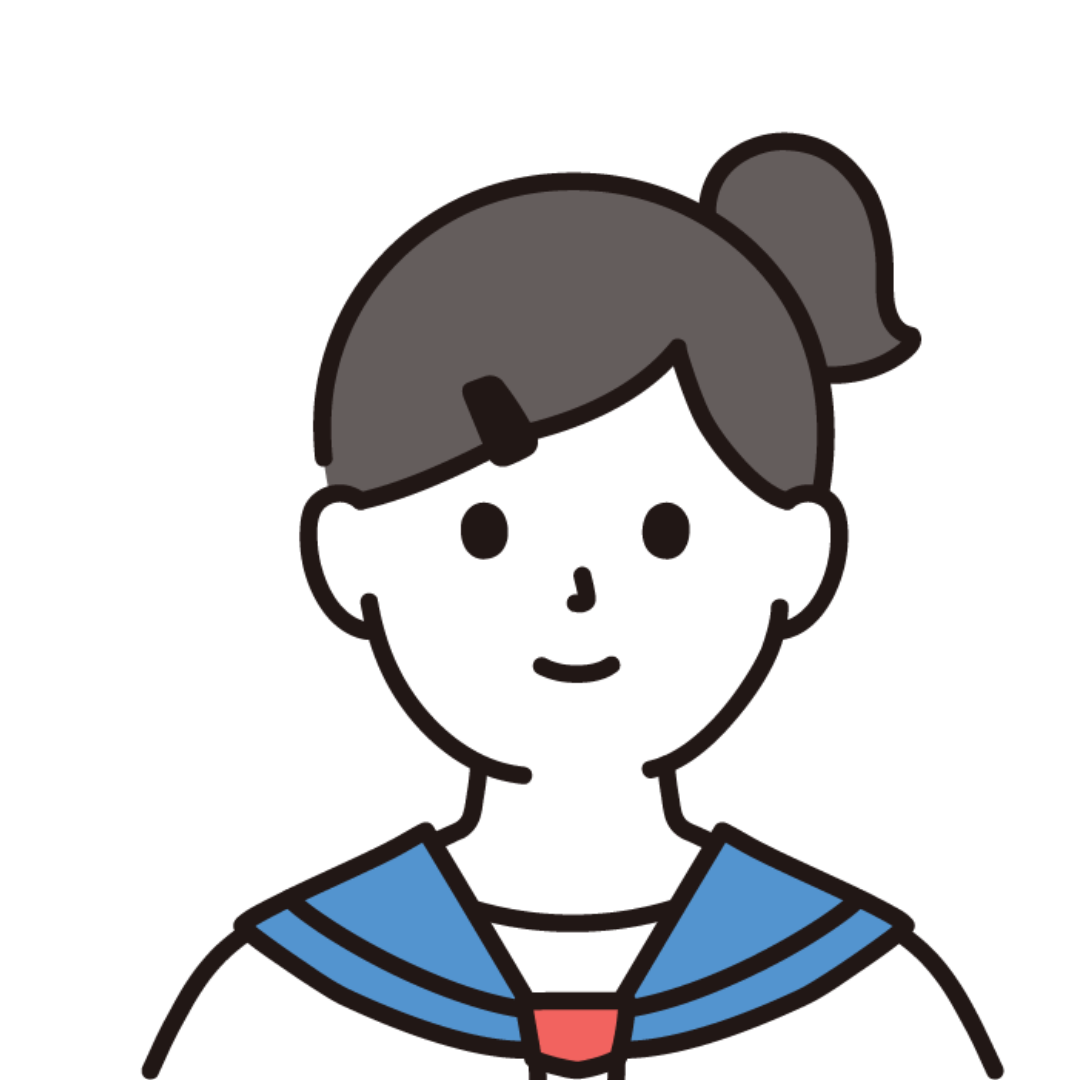
この情報、知らないとヤバいかも…

みんな楽しそうなのに、自分だけ…
SNSなどでキラキラした情報を見ると、そんな焦りを感じませんか? これはFOMO(Fear of Missing Out)、つまり「取り残されることへの恐怖」と呼ばれる心理です。
そして、ここからが少し耳の痛い話になるかもしれません。
このFOMOを感じやすい背景には、もしかしたら「自分への自信のなさ」や「他人からの承認を強く求めてしまう気持ち」が隠れている可能性があります。
流行に乗ることで、
「イケてる自分」
「ちゃんと情報感度の高い自分」
「みんなと同じように楽しめている自分」
…を演出し、一時的に安心感や自己肯定感を得ようとしているのかもしれません。
正直に自分自身の心に問いかけてみてください。
「本当にそれが欲しいのか?」「本当にそれが楽しいのか?」それとも、「流行に乗っている自分」でいることで、何かを満たそうとしているのか…?
もちろん、流行を純粋に楽しむことは素晴らしいことです。でも、もし「追いかけないと不安」「合わせないと落ち着かない」と感じるなら、それは自分の心の声に耳を傾ける合図かもしれません。

うーん、これはちょっとドキッとした。正直、僕も流行ってるものを持つと、ちょっとだけ自分が良く見えた気がする…みたいな気持ち、あったかも(汗)。
本当は何がしたいのか、ちゃんと考えるの、大事だね…。
3. 情報のシャワー、気づけばびしょ濡れ?SNS時代の見えない流れ

現代は、スマホを開けば、次から次へと情報が流れ込んできます。特にSNSは、私たちの興味や関心を学習して、「おすすめ」をどんどん表示してくれますよね。
これは便利な反面、気づかないうちに、特定の情報ばかりに囲まれてしまう「フィルターバブル」という状況を生み出します。
みんなが同じような情報を見て、同じような話題で盛り上がっていると、それが世の中のすべてのように感じてしまう。
そして、「これが今の普通なんだ」「これが正しいんだ」と思い込みやすくなります。
とくにXとかでも見られがちな印象があります。(個人的に)
アルゴリズムによって作られた見えない「流れ」に乗って、いつの間にか、自分の意思とは関係なく、特定の流行に引き寄せられている…なんてことも、実はよく起こっているのかもしれません。(参考:フィルターバブルやSNSのアルゴリズムに関する研究)

確かに!おすすめに出てくる動画とか見てると、いつの間にか時間経ってるし、なんかみんな同じようなこと言ってる気がする時あるよね…。
僕は、Googleのアカウントいくつか作成して色々変えてみるのも、面倒だけど新しい動画とか自分とは違う世界が見つかって良いなと思うよ。
4. じゃあ、どうすればいい?“自分軸”でいるためのヒント

ここまで、流行に流されてしまう理由を見てきました。じゃあ、どうすれば情報の波に溺れずに、自分らしくいられるのでしょうか?
特別なことは必要ありません。日常の中で、少しだけ意識を変えてみることです。
① ちょっと立ち止まって、自分の心に聞いてみる
「これ、本当に欲しい?」「本当に楽しい?」と、流行に触れたときに一呼吸置いて自問自答するクセをつけてみましょう。「なんとなく」で飛びつく前に、自分の素直な気持ちを確認する時間を作るんです。
② 「知らない」ことを怖がらない
世の中のすべての流行を追うなんて、どだい無理な話です。「知らない情報があっても大丈夫」「全部を好きになる必要はない」と、少し肩の力を抜いてみませんか? FOMOを感じたら、「まあ、いっか」と受け流す練習も大切です。
③ 情報との「距離」を意識する
スマホを見る時間を決めたり、寝る前はSNSを見ないようにしたり。意識的に情報から離れる時間(デジタルデトックス)を作ることで、頭の中がクリアになり、周りの声に惑わされにくくなります。
④ 自分の「好き」や「心地いい」を大切にする
流行とは関係なく、自分が本当に好きなこと、心からリラックスできること、夢中になれることに時間を使ってみましょう。自分の「好き」で心が満たされていれば、外からの情報に過剰に反応しにくくなります。
⑤ 小さな「自分で決めた」を積み重ねる
今日のランチ、読む本、休日の過ごし方…どんな小さなことでもいいので、「自分で考えて、自分で決める」経験を増やしていくこと。これが、少しずつ「自分軸」を育てていくトレーニングになります。

なるほど…!全部をいきなりやるのは難しくても、まずは「本当にそうかな?」って一瞬考えるだけでも違いそう!自分の「好き」を大事にするっていうのも、すごくいいなぁ。僕も、もっと好きな読書の時間、増やしてみようかな。
さいごに
流行に流されてしまうのは、人間の自然な心の動きの一部です。だから、そんな自分を責める必要はまったくありません。
大切なのは、その仕組みを知った上で、「今の自分は、どうしたいんだろう?」と、時々立ち止まって考えてみること。
流行をうまく楽しむことも、距離を置くことも、どちらも間違いではありません。あなた自身が心地よいと感じるバランスを見つけることが、一番大切なんです。
この記事が、情報に振り回されず、もっと軽やかに、あなたらしく毎日を過ごすための、小さなきっかけになれたら嬉しいです。

流行を全部シャットアウトするんじゃなくて、うまく付き合っていく感じがいいよね。これからも一緒に、少しずつリラックスできるヒントを探していきましょう!
▼ あわせて読みたい記事
【参考文献・引用元(一部抜粋・敬称略)】
- 社会的同調に関する心理学研究(例: Asch, S. E. の研究など)
- 脳の報酬系(ドーパミン)と社会的承認に関する神経科学的研究(例:Sherman, L. E., et al. (2016) など)
- FOMO(Fear of Missing Out)に関する心理学研究
- フィルターバブルやSNSアルゴリズムの影響に関する研究(例: Appel et al., 2020 など)
- 草薙龍瞬『反応しない練習 あらゆる悩みが消えていくブッダの超・合理的な「考え方」』(KADOKAWA/中経出版)
- ターリ・シャーロット『事実はなぜ人の意見を変えられないのか』(白揚社)
※本記事は特定の研究成果を断定するものではなく、読者の皆様のウェルビーイング向上のためのヒントとして情報を提供しています。正確な情報提供に努めておりますが、医学的・専門的なアドバイスに代わるものではありません。


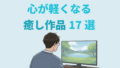
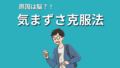
コメント