もっと頑張らなきゃ
もっと手に入れなきゃ…
なんだか息苦しさを感じていません?
この「多すぎる」現代社会は、ちょっとしんどい場面も多いかもしれません。

なんだか、もう疲れたな…

もっとシンプルに、穏やかに暮らしたい…
その根本原因は「持ちすぎ」「抱えすぎ」にあるのかも。
実は、最新の心理学や脳科学の研究では、「増やす」ことよりも、むしろ「減らす」ことの方が、私たちの心の健康や幸福感を高める可能性が示唆されているんです。
この記事では、「減らす」ことで得られる意外なメリットと、今日からできる具体的なステップを、科学的な視点も交えながら、皆さんと一緒にじっくり考えていきたいと思います。

僕も気づくとスマホ見ちゃったり、やらなきゃいけないことで頭がいっぱいになったり…。
✅この記事は、こんな方におすすめです
・刺激を減らして穏やかに過ごしたいと感じている方
・心の余裕をなくしている方
・シンプルな生き方に興味がある方
今日からできる簡単な「減らす」5ステップ
①モノを「1つ買ったら1つ手放す」
②寝る前のスマホ時間を減らす
③甘い飲み物を水やお茶に変える
④明日のタスクを3つに絞る
⑤1日の終わりに「良かったこと」を3つ思い出す
【おすすめ本・ガジェット】
「減らす」ことのヒントになりそうなものを、厳選してみました。
📚 書籍『ぼくたちに、もうモノは必要ない。』佐々木典士 著
「ミニマリズム」という考え方を、すごく分かりやすく、そして温かく教えてくれる本です。モノを減らすことで、本当に大切なものが見えてくる感覚…読んでいてハッとさせられました。持ち物を見直すきっかけにぜひ。
💻 アプリ『Forest: Stay focused』
ついついスマホを触っちゃう…という方におすすめ。スマホを触らない時間に応じて、アプリ内で木が育つんです。集中したい時、僕もよく使ってます。枯らさないように頑張るのが、ちょっと楽しい。デジタルデトックスの第一歩に。
1. なぜ私たちは「増やしすぎて」しまうの? – つい求めてしまう心のブレーキの外し方

「減らす方が良い」と頭では分かっていても、気づけばモノが増えていたり、新しい情報を追いかけてしまったり…。
「もっと欲しい」「足りない」と感じてしまうのは、一体なぜなのか?
実は、私たちの脳や心には、そうなりやすい「クセ」のようなものがあるんです。
例えば、
「損失回避バイアス」。
これは、何かを手に入れる喜びよりも、「失うことへの痛み」を強く感じてしまう心の働きです。
「もったいない」「いつか使うかも」と思って、なかなかモノを手放せないのは、このバイアスが影響していると言われています。
また、新しい情報や刺激に触れると、脳の中では「ドーパミン」という快感物質が放出されます。
これが「もっと!もっと!」という欲求につながり、SNSの通知が気になったり、次々と新しいものを買いたくなったりする一因と考えられています。
さらに、私たちは無意識のうちに周りの人と自分を比べてしまう「社会的比較」という性質も持っています。「あの人が持っているから欲しい」「これがないと時代遅れかも」と感じてしまうのも、自然な心の動きなんですね。
こんな風に、私たちの心は、放っておくと「もっと増やしたい!」という方向に進みやすいようにできているのかもしれません。

確かに「限定品」とか言われると欲しくなっちゃうし、SNS見てると他の人が羨ましくなったり…。無意識にそうなってたんですねぇ。
2. えっ、これも逆効果だったの!? 「減らす」ことで得られる驚きのメリット5選
では、意識的に「減らす」ことを選ぶと、私たちの心と身体にはどんな良い変化が起こるのでしょうか?
科学的な研究で分かってきた、主なメリットを5つご紹介します。
「えっ、これも良くなかったの?」と意外に思うこともあるかもしれませんよ。
メリット1:スクリーンタイム削減 → 脳が休まり、ぐっすり快眠へ

夜寝る前までスマホを見ていませんか?
実は、スマホやPCの画面から出るブルーライトは、私たちの脳に「まだ昼間だよ!」と勘違いさせてしまい、自然な眠りを誘うホルモン「メラトニン」の分泌を邪魔してしまうことが分かっています。
ある研究では、寝る前のスクリーンタイムを意識的に減らしたグループは、そうでないグループに比べて、睡眠の質が向上し、気分の落ち込みやストレスレベルも改善したという結果が出ています。
つまり、ただスマホ時間を減らすだけで、脳がしっかり休息できるようになり、心も安定しやすくなる可能性があるのです。
ポイント:寝る前のスマホ時間を減らすだけで、睡眠の質と心の安定につながる。

眠りが浅いなって感じてたのは、もしかしてこれが原因だったのかも…?
メリット2:甘いもの控えめ → 気分の波が穏やかに、集中力も安定

疲れた時やイライラした時、甘いものを食べるとホッとする…という方も多いかもしれません。
でも、ちょっと待ってください。
糖分の多いものを摂ると、一時的に血糖値が急上昇し、その後急降下します。この血糖値の乱高下が、実は気分の波(イライラしたり、急に落ち込んだり)や、集中力の低下を引き起こす原因になることがあるんです。
さらに、長期的に見て、糖分の多い食事を続けている人は、うつ病などの精神的な不調のリスクが高まる可能性も指摘されています。
特に加工食品や甘い飲み物には、思った以上に多くの糖分が含まれていることが多いので注意が必要です。
ポイント:糖分の摂取を意識的にコントロールすることで、気分の安定と集中力維持が期待できる。

疲れた時に甘いもの!って思ってたけど、逆効果なこともあるのか…。うーん、おやつの選び方、真剣に考えてみようかな。いつも飲んでるカフェラテのシロップも、ちょっと減らしてみよう…。
メリット3:タスクを厳選 → 脳の「決断疲れ」を防ぎ、本当に大切なことに集中
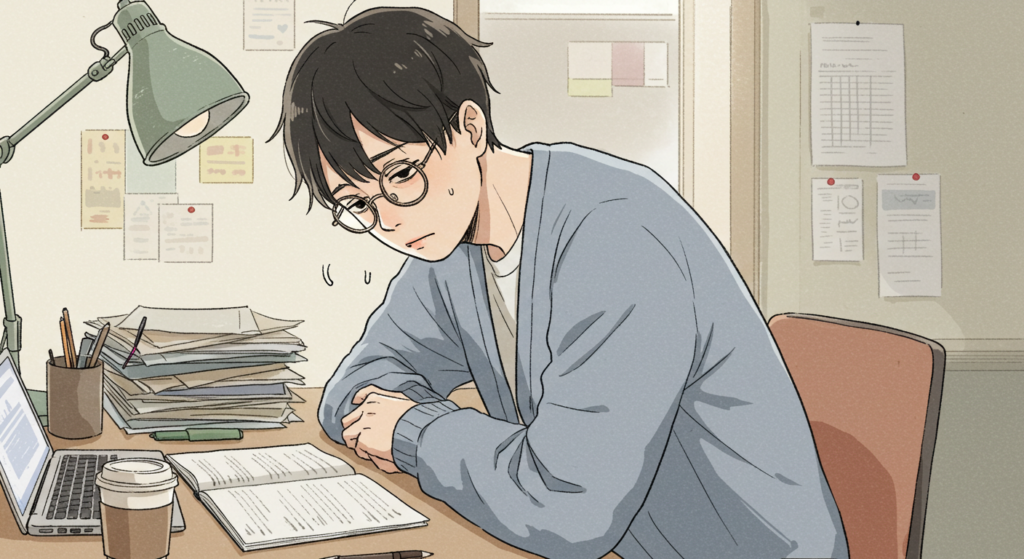
「あれもこれもやらなきゃ!」と、常にたくさんのタスクを抱えていませんか?
同時に複数のことをこなそうとする「マルチタスク」は、一見効率的に見えますが、実は脳に大きな負担をかけています。
研究によると、タスクを切り替えるたびに集中力が中断され、かえって全体の生産性が落ちたり、ミスが増えたりすることが分かっています。
また、私たちは一日に何度も大小さまざまな決断をしていますが、その回数が多すぎると「決断疲れ」という状態に陥ります。これは、意志力や集中力といった脳のエネルギーが消耗してしまい、いざという時に重要な判断ができなくなってしまう現象です。
抱えるタスクや選択肢を意識的に減らすことは、脳の疲労を防ぎ、本当に大切なことに集中するためのエネルギーを温存することにつながるのです。
過剰な仕事量がメンタルヘルスに悪影響を与えることも、WHO(世界保健機関)などが指摘しています。
ポイント:抱えるタスクや選択肢を減らすことで、脳のエネルギー消耗を防ぎ、生産性が向上する。

わかる…。やることリストが長すぎると、もう何から手をつけていいか分からなくなって、結局何も進まない、みたいなこと、僕もよくあります…。
マルチタスクって、できる人カッコイイと思ってたけど、実は脳には優しくなかったんだな。減らす勇気も大事なんですね。
メリット4:「どうせ自分なんて…」思考をストップ → 心穏やか、自信も回復

「どうせ自分には無理だ…」「また失敗したらどうしよう…」
そんなネガティブな考えが、頭の中でぐるぐると回り続けてしまうことはありませんか?
こうした思考のクセは、実は意識的に変えていくことができるんです。
認知行動療法(CBT)という心理療法では、自分の考え方のパターンに気づき、それが本当に事実に基づいているのか、別の考え方はできないかと検討することで、よりバランスの取れた見方を身につける練習をします。
多くの研究で、CBTは不安や気分の落ち込みを和らげるのに効果的であることが示されています。
また、「今日も一日頑張ったな」「あの時、親切にしてもらえて嬉しかったな」といった、日々の小さな「良かったこと」や「感謝」に目を向けることも、心の状態をポジティブに保つのに役立つことが分かっています。
ポイント:自分の思考パターンに気づき、ネガティブな思い込みを減らす練習で、心の安定を取り戻せる。

ネガティブ思考、僕も得意分野です(苦笑)。
「どうせ無理」って思う前に、「本当にそうかな?」って一回立ち止まってみるクセをつけたいな。
メリット5:モノを手放す → 頭スッキリ、心に「余白」が生まれる
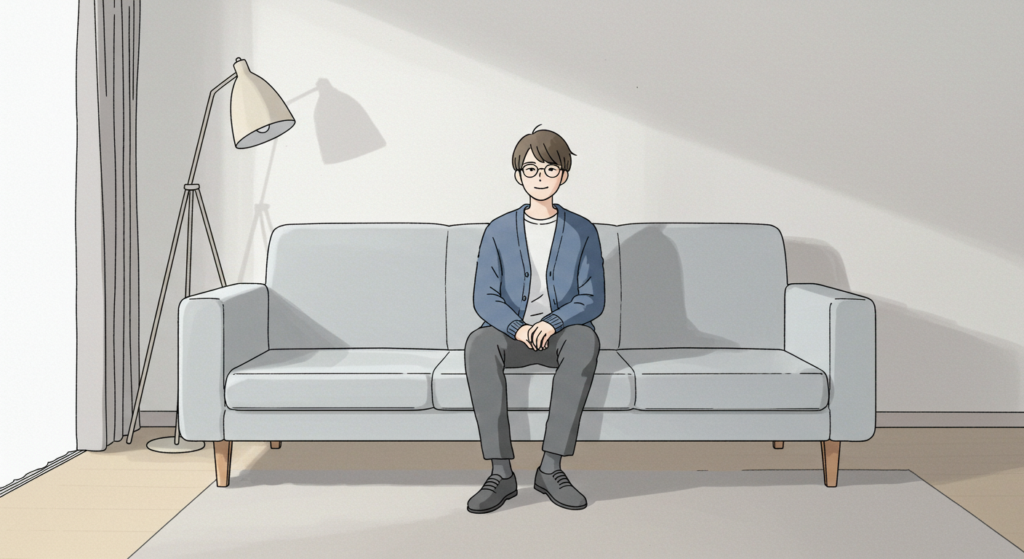
部屋がモノで溢れかえっていると、どうでしょう?
なんとなく落ち着かない、集中できない…と感じることはありませんか?
実は、私たちの脳は、視覚的な情報が多い環境にいると、無意識のうちにそれらを処理しようとしてエネルギーを使ってしまいます。
ある研究では、物理的に散らかった環境は、ストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌量を高める可能性があることも示されています。
逆に、モノを減らして空間をシンプルにすることは、脳の認知的な負担を減らし、注意力を散漫にさせる刺激を少なくする効果があります。
それだけでなく、「あれを管理しなきゃ」「これを片付けなきゃ」といった心の負担からも解放され、精神的な「余白」が生まれるのです。
実際に、ミニマリズム(最小限のもので暮らすライフスタイル)を実践している人々は、物質的な所有を減らすことで、精神的な自由度や幸福感が高まったと感じていることが多いという研究報告もあります。
ポイント:物理的な空間を整えることは、頭の中と心の整理にもつながり、精神的な余裕を生み出す。

確かに、部屋が散らかってると、なんか気持ちもザワザワ…。
探し物が見つからない!とか、それだけでストレスだし。モノを減らすのって、ただスッキリするだけじゃなくて、心にも良い影響があるんだなぁ
3. 無理なくできる!「減らす」を始める小さな一歩
「減らす」ことのメリットは分かったけど、いざやるとなると、何から手を付ければいいか迷ってしまいますよね。
ここでは、特に刺激に敏感な内向型さんやHSPさんでも、無理なく始められる具体的なステップを5つご紹介します。
完璧を目指さず、「ちょっと試してみるか」くらいの軽い気持ちで始めてみてください。
ステップ1:【デジタル】寝る前1時間は「デジタル・オフタイム」

まずは、質の高い睡眠を取り戻すことから始めましょう。
寝る1時間前になったら、スマホやPC、タブレットの電源をオフにするか、通知が目に入らない場所に置きます。
そして、代わりに本を読む、穏やかな音楽を聴く、温かいハーブティーを飲む、軽いストレッチをするなど、心がホッとする時間を作りましょう。

でも、いきなりゼロは難しくても、まずは30分前から始めてみるとかでもいいのかもね。寝る前のストレッチ続けてみよう。
ステップ2:【食】まずは飲み物から「砂糖さよなら」チャレンジ

いきなり食事全体を変えるのは大変ですよね。
なので、まずは普段飲んでいるものから見直してみませんか?
甘いジュースや炭酸飲料、加糖のコーヒーや紅茶、エナジードリンクなどを、水やお茶、無糖の炭酸水、ブラックコーヒーなどに置き換えるだけでも、知らず知らずのうちに摂っていた糖分の量をかなり減らすことができますよ。

いつもコンビニで買ってる甘いカフェラテを、ブラックコーヒーに変えてみることから始めようかな。意外と、それで気分もスッキリ。
ステップ3:【タスク】明日の「やることリスト」は、厳選して3つだけ

「あれもこれも…」とたくさんのタスクをリストアップすると、それだけで圧倒されてしまいますよね。
そうではなく、明日絶対に終わらせたいこと、あるいは自分にとって一番重要だと思うことを
「3つだけ」に絞ってみましょう。
優先順位が明確になり、一つ一つ達成する喜びも感じやすくなります。
「ポモドーロ・テクニック」(25分集中して5分休憩を繰り返す)を取り入れるのも、集中力を保つのにおすすめです。

いつもリストが長すぎて、結局どれも中途半端になっちゃうこと多いから…。一番大事なことを見極める練習にもなりそう。
ステップ4:【思考】1日の終わりに「今日の良かったこと」を3つ思い出そう

ネガティブな考えにとらわれがちな方は、「良かったこと探し」の練習をしてみましょう。
寝る前や一日の終わりに、ノートやスマホのメモ帳に、
今日あった
「ちょっと嬉しかったこと」「感謝したこと」「うまくいったこと」などを、どんな小さなことでもいいので3つ書き出してみるのです。
これを続けることで、物事の良い側面に自然と目が向くようになり、心が少しずつ上向きになっていくはずです。

良かったこと3つかぁ。
「天気が良くて気持ちよかった」とか、「ご飯が美味しかった」とか、そういうのでもOK。 探すクセをつけるのが大事なのかも。
ステップ5:【モノ】「1つ買ったら、1つ手放す」を合言葉に

モノをなかなか減らせない…という方は、まず「これ以上増やさない」ことから始めてみませんか?
新しいモノを何か1つ買ったら、代わりに同じカテゴリーの古いモノや使っていないモノを1つ手放す、という「1イン1アウト」のルールを試してみるのです。
例えば、新しい服を1枚買ったら、着ていない服を1枚処分する、といった具合です。
まずはクローゼットだけ、本棚だけ、のように範囲を限定して始めると、無理なく続けやすいですよ。

「1つ買ったら1つ手放す」…
なるほど! これなら、罪悪感なく新しいものを買えるし、モノが増え続けることも防げるね! まずは、溜まってるTシャツからやってみよう。
まとめ:手放すことで、もっと豊かになれる

私たちはつい、「もっと、もっと」と足し算で物事を考えがちです。
でも、情報も、モノも、やることも、何もかもが「多すぎる」と感じるこの時代においては、むしろ勇気を持って「引き算」をすること、つまり「減らす」ことが、心の平穏を取り戻し、自分にとって本当に大切なものを見つけるための鍵になるのかもしれません。
①夜のスマホ時間を少しだけ減らしてみる。
②いつも飲む甘いジュースを、水に変えてみる。
③明日のタスクを、3つに絞ってみる。
④1日の終わりに「良かったこと」を3つ思い出す
⑤モノを「1つ買ったら1つ手放す」
「減らす」ことは、何かを我慢したり、失ったりすることではありません。
それは、自分にとって本当に価値のあるもの、心地よいと感じるものを選び取り、より軽やかに、より自分らしく生きていくための、とても積極的で、良い選択です。
この記事が、あなたの心が少しでも軽くなり、「なんだか、いらないかも?」と、身の回りのものや情報と向き合うきっかけになれば、とても嬉しいです。

「減らす」って、我慢するんじゃなくて、自分を大切にするための方法だね。
僕も、自分のペースで「ちょうどいい」を見つけていきたいな。焦らず、できることから! これからも一緒に、少しずつ楽に生きるヒントを探していきましょう!
▼ あわせて読みたい記事
【参考文献・引用元(一部抜粋)】
参考文献・引用元
Knüppel, A., et al. (2017). Sugar intake from sweet food and beverages, common mental disorder and depression… Scientific Reports. [PMC5532289]
Lustig, R. H., et al. (2014). The Impact of Free and Added Sugars on Cognitive Function… Nutrients. [PMC10780393] (※直接の引用ではないが糖分と認知機能の関連研究として参考)
Martin, H., et al. (2022). Effects of reducing digital screen use on well-being, mood, and biomarkers of stress… Journal of Medical Internet Research. [Nature s44184-022-00015-6]
Ohio State University Wexner Medical Center. How screen time affects your health. (※出典[4]として利用)
[座位時間削減に関する研究 – 参考] BMJ Open e041327
[座位時間削減に関する研究 – 参考] ScienceDirect S0197455619300632
World Health Organization (WHO). Mental health at work. (※出典[7]として利用)
Chong, E. S. K., et al. (2022). Workload and Mental Well-Being of Homeworkers… International Journal of Environmental Research and Public Health. [PMC9524528] (※出典[8]として利用)
Chand, S. P., et al. (2021). Cognitive behavioral therapy for management of mental health and stress-related disorders… StatPearls. [PMC8489050] (※出典[9]として利用)
[マインドフルネスに関する研究 – 参考] PMC7511255
[マインドフルネスに関する研究 – 参考] PMC5679245
[ポジティブ感情に関する研究 – 参考] PMC3122271
Huffman, J. C., et al. (2013). The Role of Positive Emotion and Contributions of Positive Psychology in Depression Treatment. Primary Care Companion for CNS Disorders. [PMC3866689] (※出典[13]として利用)
Sin, N. L., & Lyubomirsky, S. (2009). Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms with positive psychology interventions: A practice-friendly meta-analysis. Journal of Clinical Psychol1ogy. [PsycNet 2011-06862-001] (※出典[14]として利用)
Cleveland Clinic. Cognitive Behavioral Therapy (CBT): What It Is & Techniques. (※出典[15]として利用)
Mayo Clinic. Cognitive behavior therapy. (※出典[16]として利用)
[糖分削減技術 – 参考] OSU Food Blog
[糖分削減技術 – 参考] Nestle Press Release
Hackensack Meridian Health. Screen Time and Mental Health: Why Cutting Back Matters. (※出典[19]として利用)
[アートセラピー – 参考] BMJ Open e043669
[アートセラピー – 参考] PsycNet 2018-09879-001
[自然との触れ合い – 参考] Mental Health Foundation UK
[自然との触れ合い – 参考] JECH 72(10):958
American Psychological Association (APA). Multitasking: Switching costs. (※出典[24]として利用)
[自然との触れ合い – 参考] PositivePsychology.com
Roster, C. A., et al. (2016). The dark side of home: Assessing possession “clutter” on subjective well-being. Journal of Environmental Psychology. (※2出典[26]として利用)
Lloyd, K., & Pennington, W. (2020). Towards a Theory of Minimalism and Wellbeing. International Journal of Applied Positive Psychol3ogy. (※出典[27]として利用)
[アカデミック・バウンシー – 参考] Journal of School Psychology, 46(1), 53-83.
[デジタルミニマリズム – 参考] Newport, C. (2019).
[認知負荷理論 – 参考] Educational Psychology Review, 29, 393-405.
[物質主義と幸福感 – 参考] Journal of Personality and Social Psychology, 107(5), 879-924.
[シンプルな生活と幸福感 – 参考] Social Indicators Research, 74(2), 349-368.
Pignatiello, G. A., et al. (2020). Decision fatigue: A conceptual analysis. Journal of Health Psychology. (※出典[33]として利用)
[ポジティブ感情の拡張形成理論 – 参考] American Psychologist, 56(3), 218-226.
[認知負荷理論 – 参考] Educational Psychologist, 38(4), 229-237.
McMains, S. & Kastner, S. (2011). Interactions of top-down and bottom-up mechanisms in human visual cortex. Journal of Neuroscienc4e. (※出典[36]として利用)
Fisher, A. V., et al. (2014). Visual environment, attention allocation, and learning in young children… Psychological Science. (※出典[37]として利用)
[不安と認知負荷 – 参考] Educational Technology & Society, 12(4), 179-193.
[感情と認知負荷 – 参考] Journal of Educational Psychology, 104(2), 287-305.
[感情と認知負荷 – 参考] Learning and Instruction, 22(6), 472-482.
[意志力 – 参考] Baumeister, R. F., & Tierney, J. (2011).
[ウェルビーイングと認知負荷 – 参考] Frontiers in Education, 4, 121.
[物質主義と環境 – 参考] Journal of Environmental Psychology, 36, 186-194.
[デジタルミニマリズム – 参考] Das, M. (2023).
※ここに記載したのは参考情報の一部です。特定の研究成果を断定するものではなく、あくまで皆さんのウェルビーイング向上のためのヒントとしてご紹介しています。心身のことで気になる点があれば、専門家にご相談ください。



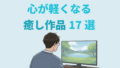
コメント