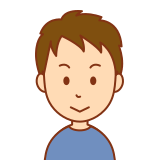
一人の時間がないと無理…
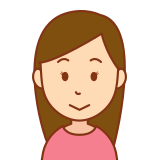
人混みや騒がしい場所は苦手…
日々のストレスを解消し、心を穏やかに保つための効果的な方法を探していませんか?
実は、塗り絵や文章を書くこと、楽器の練習といった、一人で静かに楽しめる活動が、私たちのメンタルヘルスや自己成長に良い影響を与えることが研究で示されています。
この記事では、そうした研究結果を分かりやすく紹介し、内向的な私たちが持つ「深く考える力」を活かしながら、心豊かに過ごすためのヒントを探っていきます。

内向的な人ほど家でできる趣味を見つけよう
✅1分要約
①内容➤「静かな趣味」がメンタルケアやセルフケアにどう役立つかを紹介
②取り組み➤ 塗り絵(気分改善)、書くこと、音楽(達成感)、多様な趣味(心の回復力UP)などが心に良い影響を与えることが分かっています。
③静かな趣味➤一人で深く集中でき、心地よい刺激レベルで取り組める「静かな趣味」は、内向型やHSPの気質と相性が良いです。
④無理なく続けるコツ➤楽しむことを最優先に、手軽さ、日常への組み込みやすさを意識し、時にはAIも活用するのがおすすめです。
1. 静かな活動が心にもたらす嬉しい効果

では、具体的にどのような活動が私たちの心に良い影響を与えてくれるのでしょうか?いくつかの研究から、興味深い結果が見えてきました。
1-1. 塗り絵で気分転換:色と形がもたらす癒やし
子どもの頃、夢中になった塗り絵。実は大人にとっても、手軽にできるメンタルケアになるようです。ある研究では、特に自由に塗る形式の塗り絵に取り組んだ後、ネガティブな気分や不安感が減少したと報告されています(Nozue et al., 2018)。
決められた枠にとらわれず、好きな色で自由に表現することが、心を落ち着かせ、リラックス効果につながるのかもしれません。画材を用意するハードルも低く、今日からでも始めやすいのが魅力ですね。

子供のころにポケモンの塗り絵してたなぁ…
1-2. 書くことの力:SNSでの感情表現と心の健康
自分の気持ちやストレスについて「書く」ことも、心の整理に役立ちます。特にSNSでストレス体験について書くことを調査した研究(Zheng et al., 2020)では、興味深い結果が出ています。「中程度の深さ」で自己開示(自分のことを話すこと)をした場合、抑うつ感が低くなる傾向が見られました。
しかし一方で、あまりにも深いレベルで書きすぎると、逆に孤独感が高まる可能性も示唆されています。
SNSで感情を表現する際は、どこまで、どのように書くかが、心の健康にとって重要なポイントになりそうです。誰かに見せるためというより、自分の気持ちを整理する手段として「書く」ことを捉えると良いかもしれませんね。

自分と見てくれる人が、心からリラックスした毎日を送れるように僕は発信しているよ
1-3. 音楽や多様な趣味:達成感とレジリエンスを高める
楽器の練習や、様々な趣味を持つことも、私たちの心にポジティブな影響を与えるようです。例えば、楽器の練習は、仕事における達成感と関連があることが示唆されています(森, 2022)。
練習を通して得られる「できた!」という感覚が、仕事への自信にも繋がるのかもしれません。また、特定の趣味一つだけでなく、多様な余暇活動に積極的に取り組んでいる人ほど、抑うつ感が低く、レジリエンス(心の回復力)が高い傾向にあることも報告されています(滝口 et al., 2021)。
いろいろな活動に少しずつ触れてみることで、心のバランスが取りやすくなるのかもしれませんね。

僕はピアノとか上手くはないけど、弾いていると気分が良くなるんだよなー不思議
2. 内向性と深い思考力を活かす趣味選び

紹介してきた塗り絵、書くこと、音楽、多様な趣味といった活動は、特に私たち内向的なタイプにとって、取り組みやすく、メリットを感じやすいものかもしれません。
それはなぜでしょうか?そして、どうすれば無理なく続けていけるのでしょうか?
2-1. なぜ内向的な人に向いているのか?
内向的な人は、外からの刺激よりも、自分の内面の世界に意識が向きやすいと言われています。多くの人と賑やかに過ごすよりも、一人で静かに何かに没頭する時間を好む傾向があります。
一人の時間を豊かにする: 塗り絵や楽器の練習、文章作成などは、基本的に一人で集中して取り組める活動です。外部のペースに合わせる必要がなく、自分のペースでじっくりと楽しめます。これは、エネルギーを消耗しやすい内向的な人にとって、心地よい時間となり得ます。
深く考える力を活かせる: 内向的な人は、物事を深く掘り下げて考えたり、感じたりする力を持っています。文章を書いて自分の内面と向き合ったり、音楽の繊細な表現を探求したりする活動は、まさにその力を活かせる場と言えるでしょう。研究で示された「深い認知的な省察(cognitive reflection)」を伴う活動がもたらすメリットは、内向的な人の特性と相性が良いと考えられます。
心地よい刺激レベル: HSP気質を併せ持つ人にとっては特に、刺激の量を自分でコントロールできることも重要です。これらの静かな活動は、過度な刺激が少なく、安心して取り組めるものが多いでしょう。

不思議とアートや音楽などクリエイティブな活動は集中できる
2-2. 無理なく続けるためのヒント
「始めても、なかなか続かない…」という経験はありませんか? 調査結果も踏まえつつ、長続きさせるためのヒントを考えてみましょう。
「好き」と「手軽さ」を大切に: まずは、自分が純粋に「楽しそう」「やってみたい」と感じることから始めるのが一番です。塗り絵のように、初期投資が少なく、すぐに始められるものは、最初のハードルが低いかもしれません(Nozue et al., 2018)。
日常への組み込みやすさ: SNSでの短い文章作成のように、日々の生活の中に簡単に組み込める活動は続けやすいでしょう(Zheng et al., 2020)。例えば、「寝る前に5分だけ日記を書く」「通勤中に楽器練習の動画を見る」など、小さな習慣にしてみるのがおすすめです。
「一つ」にこだわらない: 様々な余暇活動に取り組むことが、心の回復力につながるという研究結果もありました(滝口 et al., 2021)。「これ」と決めつけず、その時々の気分に合わせて、いくつかの活動を柔軟に楽しむのも良い方法です。
完璧を目指さない: 最初からうまくやろうと気負わないことも大切です。楽しむこと、リラックスすることを第一に考えましょう。

誰かから見られるとか認められなくても、自分を満たすことができればとりあえずOKってことだね
2-3. AIは趣味探しや継続をサポートできる?
最近話題のAI(人工知能)も、私たちの趣味探しや継続をサポートしてくれるかもしれません。
アイデア探しのお手伝い: 「静かに一人でできる趣味」「読書好きにおすすめのクリエイティブな活動」のようにAIに質問すれば、自分では思いつかなかった趣味のアイデアを提案してくれるかもしれません。
学習のサポート: 楽器の練習アプリや、文章作成をサポートするツールなど、AI技術を活用したサービスも増えています。練習の記録をつけたり、フィードバックをもらったりするのに役立つ可能性があります。
習慣化のリマインダー: スマートフォンのAIアシスタントなどに、「毎週土曜日の午後は絵を描く時間」といったリマインダーを設定してもらうのも、習慣化の一助になります。
私自身も、AIを活用して皆さんのメンタルケアやセルフケアをサポートできるようなアプリを開発中です。AIが、一人ひとりに寄り添った情報提供や、モチベーション維持を手助けする未来を目指しています。

AIに頼りすぎて、生活がほぼAI頼りになっているんだよね…
3. 私の体験談


僕の体験談を書いています。
元々、僕は内向的で人付き合いが苦手なうえ、頭の中はいつも不安の声でいっぱいでした。まるで自分だけ嫌な世界を見ているようで、そんな自分が心底嫌で、何とか変えたいともがいていました。特にHSP気質もあってか、人混みの喧騒や予期せぬ物音に消耗したり、休日はカーテンを閉め切った部屋で、ただ無気力にスマホを眺めているだけ。外に出る気力すら湧かない…ということが本当に多かったです。
そんな考えがぐるぐる渦巻いている時、藁にもすがる思いで試したのが、マインドフルネス瞑想と、自宅でできる静かな筋トレでした。 派手なことは苦手でしたが、呼吸に意識を向けたり、自分の体の感覚に集中したりする時間は、意外にも心が安らぐ感覚があったんです。
もちろん、最初は5分続けるのもやっとでしたが、諦めずに「ただ、やる」ことを繰り返すうちに、頭の中のもやもやが少しずつ、静かになっていくのを感じました。そして、できなかったことができるようになった時、例えば瞑想の時間が少し伸びただけでも、小さな、でも確かな達成感がじんわりと湧いてきたんです。
今では、意識的に『充電時間』とも呼べるような、一人で静かに過ごす時間を作るようにしています。そして、この時間はより今では進化しています。AIと一緒に、アイデアを形にするため、デジタルアートに挑戦したり、未知の音楽ジャンルを探したり…。少しずつ面白い発見に満ちたものに変わってきたと感じています。
もしあなたが、かつての私と同じように感じているなら、この記事で紹介したような『静かな時間』が、きっと変化を起こすための一歩になるはずです。

静かな時間を意識的に作るのが重要だよ
4. Q&A

Q1. 絵や音楽の才能がないと、楽しめませんか?
A1. まったく問題ありません!
大切なのは、うまくやることよりも、ご自身が「楽しい」「心地よい」と感じることです。塗り絵も、自由に好きな色を塗ることに意味がありますし、音楽も、まずは好きな曲を聴いたり、簡単な楽器に触れてみたりするところからで大丈夫です。誰かと比べる必要は全くありませんよ。
Q2. 忙しくて、なかなか趣味の時間が取れません…
A2. 最初からまとまった時間を取ろうとすると、ハードルが上がってしまいますよね。
まずは「1日5分だけ」でもOKです。例えば、寝る前に少しだけ日記を書く、通勤中に好きな音楽を1曲だけ集中して聴く、など、生活のスキマ時間に取り入れることから試してみてはいかがでしょうか。短い時間でも、意識的に自分のための時間を作ることで、気持ちが変わってくることがありますよ。
Q3. いろいろ試しても、すぐに飽きてしまいます…
A3. それも自然なことだと思います!
研究でも、多様な活動に取り組むことが心の回復力につながると示唆されていましたね(滝口 et al., 2021)。無理に一つを続ける必要はありません。その時々の気分や興味に合わせて、気軽にいろいろ試してみる、というスタンスで良いのではないでしょうか。「今はこれに興味があるな」という軽い気持ちで、柔軟に楽しむことをおすすめします。
5. まとめ
今回は、塗り絵や文章作成、音楽、多様な趣味といった、静かに楽しめる活動が、私たちの心の健康や自己成長にどのように役立つかについて、研究結果を交えながら見てきました。
これらの活動は、特に私たち内向的なタイプが持つ「深く考える力」を活かし、心地よい刺激の中で集中できるため、日々のストレス軽減や気分の安定、達成感の向上、さらには心の回復力(レジリエンス)を高める効果が期待できます。
大切なのは、完璧を目指すことではなく、ご自身が「楽しい」「心地よい」と感じる活動を見つけ、無理のない範囲で生活に取り入れていくことです。手軽に始められるものから試したり、AIなどのツールも活用したりしながら、あなたにとって最高の「心の栄養」となる時間を見つけてみてください。
この記事が、あなたが自分自身を大切にし、心穏やかに過ごすためのヒントとなれば幸いです。

趣味があれば辛いことも趣味で癒されるし大事なのでぜひ、自分なりの趣味を見つけてやってみてね。それではまた👋



コメント